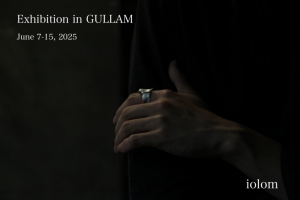こんばんは。
本日の東京は雨のち曇り。
Itouです。
今日はかなり涼しい日ですね。
梅雨時期はまだ今日のように気温が下がる日も
あったりするので羽織ものがまだ欠かせませんね。
さて、前回の入荷でご好評を頂き早々にsold outした
Eyewearブランドのtsugái(ツガイ)が入荷致しました。
今回はsold outしたBlackとMatte Blackの他に
新色のDark Grayが入荷しております。
と言いつつBlogでご紹介する前に
Blackはsold outしてしまいました。。。
このブランド、前回のBlogでも書きましたがかなりクレイジー(非常にいい意味で)です。
おそらく世界中探してもこのようなブランドは他には無いと思います。
ブランドというより職人、作家にほとんど近いかと思います。
職人兼デザイナーである北村拓也氏による一点もののアイウェア。
北村氏自身は眼鏡職人ですが
今回は完全別注ととして一から依頼し
サングラスを制作して頂きました。
「デザイナー(作家)は世界有数の眼鏡産地である鯖江で経験を積み、
その後フランスの老舗眼鏡工房にてオーダーメイド眼鏡の製作を行う。
帰国後、京都の伝統工芸の名工の元で丁稚修行を行い、
同時期に金工、漆工の研鑽を積む。
職人としての技術に大学在学時に学んだ高分子化学の知見を取り入れ、
「眼鏡職人 x 伝統工芸 に化学のエッセンスを」をコンセプトにブランドをスタート。
作品を含め、ケースなどの付属品まで全て自らの手で製作しています。
眼鏡としては常識を覆す24金や漆を使用した技法は唯一無二の世界観をもたらします。」
<tsugái eyewear>
一般的なプラスチック枠の形状をしていますが、
作成方法は眼鏡業界の方法とは大きく異なります。
“眼鏡“ の形を工芸の技法を用いて制作されています。
基本的にデザイナー(作家)が一人で仕上げており、製作時間、
材料には一般的な眼鏡の10倍の時間、費用を要しています。
先に特にご紹介したいことを述べますと
tsugáiは素材に漆と24金、そして刀の鍔などに使われていた京象嵌(布目象嵌)という
京都の伝統工芸(現在は美術工芸品に用いられている)を使用しています。
どれも通常のアイウェアでは使われない素材、技法です。
もうやっていることがクレイジーとしか言いようがありません。。。
先にも書きましたが世界中探してもおそらくこのような作り方をしているもの
はないのではないでしょうか。
素材表記を見るとこちら。
なんだかアイウェアでは見慣れない素材がちらほら。。。
<素材>
フレーム:アセテート
蝶番:付け焼き漆、24金、洋白、鉄
テンプル芯金:鉄(リボン鋼)、24金、付け焼き漆
鋲:真鍮(頭部)、洋白(足部)
レンズ:アクリル(紫外線カット率99%以上)
今回は前回から展開しているBlackとMatte Black
そして、新色のDark Grayが入荷しています。
Blackはsold outしていますが受注生産が可能で御座います。
このブランドならではの
各ディティールをご紹介致します。
<テンプル蝶番>
一般的な蝶番は金型と呼ばれる物を作り、そこに金属を流したり、
プレスする大量生産をしております。
tsugáiでは大量生産ではなく手作りで製作しています。
洋白、鉄素材のテンプル蝶番を部品毎に準備をしロウ付けで
組み立てることにより作成(ジュエリーの作成方法)しています。
また、布目象嵌(京象嵌)という技法を用いて24金を埋め込み、漆を塗っています。
漆は焼き付け漆という技法で金属に塗っています。
工芸に詳しい人でも金属に漆を塗れる事を知らない人は多いです。
蝶番の24金は写真では分かりにくいのでかなりアップで。
赤丸の部分が24金です。
そして蝶番のコーティングは全て漆です。
24金は溶剤で接着ではなく技法で取り付けています。
<京象嵌(布目象嵌)とは>
京都で行われれいる布目象嵌を、京象嵌と呼んでいます。
本来は、日本刀の鍔などに使われていた技法ですが、現在は京都の伝統工芸品とされており、
美術工芸品として主に使われています。
その名の通り 下地(金属)に“布の目“と呼ばれるミゾを付けます。
そのミゾの数は1mmに10本程度というとても繊細なで、熟練の職人にしかできない技術となります。
このミゾが剣山の様な働きをし、金を留めています。
現在、京象嵌ができる職人は10名程度だと言われています。
京象嵌(布目象嵌)による製作風景は以下のリンクよりご覧いただけます。
動画を見ていただくと分かるかと思いますが
とてつもない細かい作業です。
普通のアイウェアではこんな作業ありませんからね(笑)
そもそも伝統工芸ですから。。。
<芯金 >
一般的な芯金はプレス加工で大量生産されています。
tsugáiでは芯金をリボン鋼と呼ばれる、バネの性質を持った鉄を削り出すことで作成しています。
また蝶番同様、京象嵌(布目象嵌)という技法を用いて24金を埋め込み、漆を塗っています。
リボン鋼を使うことにより、バネ性が上がり型崩れは起きづらくなっております。
特に横方向のバネに優れてます。
ほとんどの眼鏡は“シューティング”と呼ばれる技法により作成されています。
その一方、tsugáiでは“芯張り”と呼ばれる技法で作成しています。
また、通常の芯張りとは異なり、有機溶剤を独自の方法で組み合わすことにより、
漆(芯金)をアセテートの中に入れる事を可能としました。
これは世界中でtsugái eyewearにしか使われていない技法だと思われます。
芯金(しんがね)とはテンプルに入っている金属製の棒のことです。
こちらがそうですね。
どういうことかというとこちらの画像をご覧ください。
テンプルの中に入っているのが芯金。
tsugáiではこの芯金にも漆コーティングと24金を埋め込んでいます。
これも世界中探してもtsugáiしかやっていないことだと思います。。。
もうやっていることが変態です(笑)
<マット加工 >
Matte Blackカラーのみの加工方法です。
テクスチャーを2種類混ぜて独自の方法で全体をマットに仕上げています。
通常のマットはガラスや砂などを機械の中で打ち付けてマットにしますが、
tsugáiでは全く異なり、2種類のテクスチャーを手で削って重ね合わせているため
ひとえにマット加工と言ってもこちらはtsugái独自の加工、雰囲気に仕上がっております。
ケースや付属品ももちろん拘っています。
ケースは桐箱を使用。
桐ダンスや、桐下駄で使われてる仕上げ方、
「砥の粉(とのこ)、ロウ引き仕上げ」をしています。
眼鏡拭きは奈良の鹿の皮をなめしたセーム革を使用しています。
セーム革とは通常のなめし加工したものを再度、鱈油でなめし(二次鞣し)を行ったもので、
従来より、カメラやメガネ等のレンズ、時計や宝石等の貴金属類、
ハサミ等の刃物類、自動車やガラスを磨くものとして広く使われています。
いかがでしょうか。
かなりクレイジーなことをしているのがわかったかと思います(笑)
こんなアイウェアは世界探せど中々見つからないと思います。
高額ですがそれは素材と手間暇あってのものです。
是非、ご検討ください。
ご不明な点が御座いましたらお問い合わせください。
また、新たに取り扱うバッグブランド、
Tuforée(テュフォレ)が入荷致しました。
独特な世界観でとても雰囲気のあるブランドです。
店頭ではご覧頂けますがweb storeはもうしばらくお待ちください。
それでは失礼致します。
良い週末をお過ごしください。
【information】
この度6月7日(土)~6月15日(日)に
iolom新作の展示販売 & 受注会を開催致します。
6月7日(土)はデザイナーが在店致します。
詳細は下記リンクをご覧下さい。
https://gullam.jp/blog/iolom/243956.html